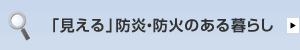ローマ時代の遺跡であるポンペイ最大の目玉は秘儀荘である。秘儀荘のもっとも奥まった場所の客室の壁一面に描かれた「ディオニソスの秘儀」と呼ばれるフレスコ壁画は見事の一語に尽きる。壁画の題材は酒と豊饒の神ディオニソス信仰の入信儀式で、等身大の女性達がポンペイ・レッドと呼ばれる限りなく朱色に近い鮮やかな赤を背景に描かれている。とにかく素晴らしい。この遺跡を訪ねた梅原龍三郎が感動したのも頷ける。
壁画で使われている赤の顔料は辰砂(しんしゃ・硫化水銀)で、これ以外にも鉛丹(えんたん・酸化鉛)が使われていた。そこで今回は「赤の美術史」と題して赤色顔料と染料の歴史を俯瞰したい。
人類史上に登場する最古の赤は、旧石器時代の洞窟壁画に使われた代赭石(だいしゃいし・赤鉄鉱)である。ラスコーやアルタミラ洞窟の壁画の赤がこれで、おそらく血液の象徴的存在として使ったと思われる。この代赭石の用途は広く、古代エジプトの王妃の化粧は目蓋に黒い方鉛鉱と緑の孔雀石の粉末を使い唇に代赭石を塗った。現代女性の定番品であるアイシャドーと口紅のルーツはここにある。
次いで登場するのが秘儀荘でも使われた辰砂と鉛丹である。前3000年紀の半ばに顔料用として採掘されているが、普及するのはギリシャ・ローマ時代である。特に辰砂は代赭石よりも鮮やかな赤が可能なので壁画等では好まれた。さらにはキリスト教時代の初期に書かれた『死海文書』も辰砂を赤インクとして用いている。
赤染料も辰砂や鉛丹と同時期に登場している。代表的なものは4種類で、具体的には、①アカネ(アカネ草)、②ケルメス(貝殻虫)、③ヘンナ(ミソハギ科低木)、④ラック(インドと東南アジアに生息する昆虫)である。テキスタイルという点で関係が深いのはトルコ赤と呼ばれたアカネで、古代エジプトやインダス文明の遺跡からアカネで染めた布地が見つかっている。このアカネは媒染剤(ばいせんざい)として明礬(みょうばん)を使うと堅牢になり、この染色技法は十字軍によってヨーロッパへ紹介された。
一方、コロンブスが1492年に発見した新大陸では、紀元前からコチニールというサボテンの一種オプンチアに付く寄生虫の仲間の小さな虫ダクチロピウスから生産していた。オプンチアは栽培できるため虫の飼育が容易である。1グラムの染料を生産するのに2000匹の雌の虫が必要であったが、ケルメス虫が1年に1回しか採取できなかったのに対してコチニール虫は数回の採取が可能であった。さらにコチニールにはケルメスの10倍の反応性染色素があるだけに主役の座を奪うのは時間の問題で、一八〇〇年代の初期にスペインがラテンアメリカの領地を失うまでは欧州市場へ向けてメキシコで盛んに生産された。その後生産はカナリア諸島に移されが、19世紀に合成アニリン染料が登場すると衰退の一途を辿っていく。

写真:ポンペイの秘儀荘のフレスコ壁画